![]()
最後の7日目になった。
本当に本当の締め切りが、あと3時間後に迫っている。
「お前、あんだけMP3ある中から、選んで載せてるでしょ」
はじめに口を開いたのは、浅川だった。
「どういう基準で選んでるわけ?」
確かにMP3のデータは、サキが連載用に起こした5人の他に、もう7人分あった。
倍率2倍越の壁である。
「浅川…、お前もうわかってるんだろ?」
コーヒーを口元に持っていき、飲まずに戻しながらサキが言った。
「ああ、まだ熱かった?」
ニヤニヤしながら浅川が指摘する。
「これだけヒントがあるんだから…次にどこに行くのかくらい、あてがつくはずだ」
まだ熱いコーヒーカップに片手をあてながら、ほんの少し苛立ったような調子でサキが言う。
どうやらサキには“次”に彼がどこに現れるのか、あてがついているらしい。
「ふふ。こういうのなんて言うんだっけ?部屋から一歩も出ないで事件を解決するってジャンル……。ああ、アームチェア・ディテクティブ?だっけ?安楽椅子探偵ってやつ」
締め切りまで…あと3時間。
この様子なら、大体書くことは決まってるんだろう。
担当の勘が、浅川にそう告げる。
その勘は何度かハズレてはいるが、今日は妙に落ち着いていた。
まあ、間に合わないならオレが書きゃいいか。
心の中で冗談めかして言う。
“彼”が、一之瀬洋平が辿った道は、決して場当たり的な適当な道ではなかった。
そして、そこで出会った人達も。
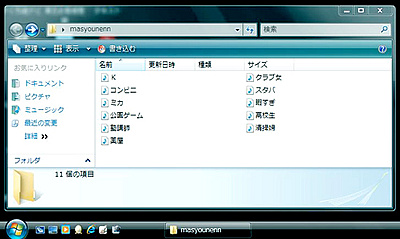
「とりあえず、お前の選抜の仕方見てると、“親が宗教入ってて…”って話しをしてる子ははじかれてる。たとえば、この子のね…」
浅川がMP3の1つをクリックする。
『ええ。話してるうちに、親の話しになって。たまたまですけど、彼の親が参加していたセミナーに、うちの親も行ってました。』
「あとは、この子とこの子も」
『ついてったことある?とか話したよ。アタシも小さい頃はよく連れてかれて、セミナーの間はそこの託児所に預けらてた、って話。』
『はい。そういう話し、しましたね。もしかして親子会の時にオレら会ってたかもねって、アイツ言ってましたけど』
逃亡する先々で“偶然”出会った人達の親が入っていた、小さな新興宗教。
それは、宗教というよりはだいぶ現代的で、カウンセリングや自己啓発セミナー、そして“悩みごと相談室”のようなものを全て混ぜこんだようなものだった。
安い会費と親しみ易い雰囲気のその宗教は、横浜を中心とした関東周辺に少しずつ広がっていた。
親が宗教に入ってる?
それもみんな同じ…。
まさか。
こんな偶然があるというのか?
その 共通点に気づいてから、横浜の信者の名簿を探すのは簡単だった。
一之瀬洋平がその名簿を手に入れたのは、多分ずっと昔のことだったのだろう。
その名簿の中には、一之瀬洋平の親の名前もあった。
そして、子供会と銘打った名簿には、信者の子供たちの名前もあった。
一之瀬洋平は、彼自身と少しでも共通点があるはずの(少なくとも彼は共通点があるはず
だと思っているのだろう)、自分と同じ“信者の子供”たちを尋ね歩いていたのだ。
その名簿には、もう1人、知っている名前があった。
小林真太郎。
彼はその宗教団体のトップである、小林正人代表の息子だった。
「そういう会話が入ってる音源を外したのは…、オレが気付いてるってことバレたくなかったからだよ」
少し熱さが落ち着いたコーヒーを、そっと口に含みながらサキが言うと、浅川は小さく息を飲んだ。まさか…。
「まさか…お前、一之瀬洋平が、あの連載読んでると思ってんの?」
マイナーな出版社の、マイナーな企画である。
そんな可能性はゼロに近い。
「いや、読んで無いことはわかってる。だけど…」
そう話すサキの横顔からは、さっきまでの苛々した様子はもうすっかり消えていた。
「だけど…どんな有り得ない可能性でも、こっちがあいつの居場所に見当ついてるって事、知られたく無かった」
穏やかな声は、まるで“知られたかった”と言っているようだった。
そうだ。
知っているんだろう?
オレがお前を捜していることを。
なあ、本当はもう、知っているんだろう?
「実は、もう見つけてある」
ため息まじりに浅川が言った。
「場所は横浜市栄区。一人暮らしの短大生の家」
それは、サキが予想していた女の子と見事に一致していた。
「先方は女の子の一人暮らしだから、こんな夜中に行って騒がれても困るし。明日その子が学校行った後、接触して連れてくる手はずになってる。
たげど… お前が行きたいなら、行ってもいい。コレ住所」
裏に何かが走り書きされたレシートを、ひらひらと指で弄びながら浅川が言う。
その薄っぺらい小さな紙に手を伸ばすと、案の定さっとかわされてしまった。
「その前に。締め切りがあるでしょ、センセイ」
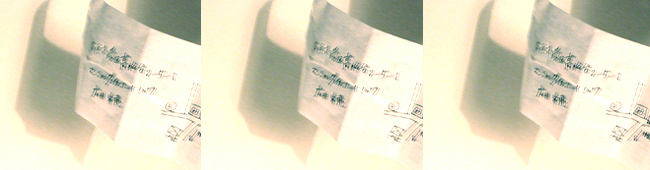
→