![]()
ざっと目を通してから、もう一度読み直してみた。
更にもう一度文字を丁寧に追いながら、背後のベッドで長くなっているであろう作者に声をかける。
「ちょっと、ねえ、これ…」
作者の男はその声に背中を向けて横たわり、微動だにしなかった。
最も、そんなことには慣れっこなようで、彼の担当編集者である浅川は1人喋り続ける。
「恋愛モノにするってのでオッケー貰ってたんだけど…お前あの場にいたでしょうが…つうか聞いてなかっただろ絶対、ちょっと、ねえ」
問いかけてはいるが、答えが返ってくることなど微塵も期待していないようだ。
「まあ…内容はなんでも良いって言うから回してもらったんだけど」
不満は多少あれど、“桐島サキ、短篇恋愛小説”とか広告打たないどいて良かったと、ほっと胸を撫で下ろす。
そもそも、何でも良いという前提があったからこそ、彼に回して貰った仕事だ。
途中で放り出しても、自分が適当に書きゃイイや…くらいの気持ちでなければ、こいつの担当など勤まらない。
「でも、まあ、いいんじゃない?なんか適当に思わせぶりだし…続きどうなんの?」
ベッドから這い出して来たらしきシーツの擦れる音を耳にしつつ、軽い調子で聞いてみた。
「これ」
乾いた声でサキが言う。
勿論“続きどうなんの?”の答えでは無い。
「何よ?」

渡されたのは、新聞の切り抜きだった。
「だから、何よこれ…」
「ここ」
「どこ?どれ?何?」
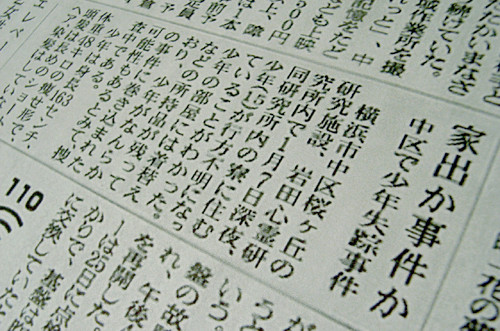
「お前…、ルポライターにでもなるつもり?」
「いや…、こいつ捜しといて」
「はあ?」
「早く捜さないと、警察か施設に取られる」
「お前さあ…ほんと、そういうの良く無いよ?」
バスルームに向かうサキの背中に向かって、浅川は形だけの説教をはじめた。
「自分でなんとかしなさいよ。なんだか知らないけど。傷?身体中に?そんなのぼせた言葉が出てくるくらい会いたいんなら、自分で探したいとか思わないのかね〜。結局いっつも部屋から一歩も出ないで散々オレこき使って、最終的に…、なんだっけ、その子が見つかったにしてもだよ、見つけるまでの過程をスッ飛ばかすのどうかと思うけど!ちょっと!ねえ!」
遠くから、シャワーの音がザーザーと聞こえる。
捜しといてって…。
遺失物でもあるまいし。
四角く切り抜かれた新聞記事を恨みがましそうに横目で見る。
でもあの人、自分でこの記事ハサミで切り抜いたのか…。
笑える。
珍しいこともあるもんだ。
「とりあえず、明日は明日で続きちゃんと書けよ」
バスルームのドア越しに声をかけると、珍しく「んー」とだけ返事が返ってきた。
ああもう。しょうがねえなあ。
いいや、一応説教しといたし。
→